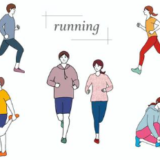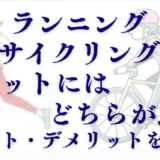スポーツとしてランニングを行っている場合、トレー二ングを行う目的を理解しておくことは大変重要です。
トレー二ングを行う目的を理解していないと、思ったような結果が残せなかったり、ケガをする可能性もあります。
この記事ではランナーのトレーニングの強度とタイプについて解説していきます。
トレーニングの強度の参考指標
イージーランニング
イージーランニングの強度はVO2maxの59~74%、最大心拍数の65~79%であるとされています。
イージーランニングは練習の大部分を楽なものにすることによって、ケガに対する耐性をつくりケガの予防に繋がるとされています。また、心臓の収縮する力は最大心拍数の60%程度で最大に達するため、きついペースで短い時間よりも楽なペースで走る時間を伸ばすことで心臓の強化が出来ます。
さらに、筋肉などに毛細血管を新しく生成し、血液が筋肉に行きわたりやすくなります。筋肉に多くの血液が行きわたることで、多くの酸素をエネルギーに転換出来るようになり運動に対する耐性が強くなります。
イージーペースは数週間・数カ月の休養からランニングに復帰した時、目標走行距離に到達するために必要な距離を稼ぐ、レースに備えて練習を抑えたい時などで行うことが多いと言われています。
マラソンペースランニング
マラソンペースはVO2maxの75~84%、最大心拍数の80~89%であるとされています。
マラソンペースの目的は実際のレースに慣れること、マラソンペースで水分をとる練習をすることであると言われています。
期待出来る身体の変化・強化はイージーランニングと大きく変わりませんが、マラソンペースの主な効果はメンタル的なもの、自信を高めるものと言えます。
走るためのエネルギーをグリコーゲンの利用が多いと、蓄えられたグリコーゲンを温存し、脂肪燃焼に頼る割合を少し増やすように身体に教えることが出来ます。
閾値ランニング
閾値ランニングはVO2maxの80~86%(熟練のランナーなら88~92%)と言われています。
閾値(いきち)ランニングは比較的速く走っていますが、ある程度の時間(20~60分程度)は維持出来るというペースです。
走るペースを上げて身体のストレスを上げていくと、筋肉内のグリコーゲンを消費してエネルギーを生成するようになります、グリコーゲンを消費してエネルギーを生成する際に身体には乳酸が生まれます。乳酸が溜まると筋肉は疲労し徐々に動かなくなっていきます。
しかし、閾値ランニングは身体内に乳酸が生じるものの、ギリギリ処理出来る強度で走るため、ある程度の運動を維持出来るというわけです。
イージーランニング・マラソンランニングは比較的楽にペースを維持できますが、閾値ランニングはある程度の熟練のランナーでも終わるのが待ち遠しいペースです。
閾値ランニングの目的は、血中の乳酸を除去し、十分に処理できる濃度よりも低く抑える能力を高めるためと言われています。(持久力の向上と考えて良い)
閾値ランニングのペースの目安は、30~60分ペースを維持出来るのかどうかということです。もし、ペースを維持できないのであれば速すぎるのでペースを落とす必要があります。
しかし、経験を積んだランナーでも、正確に閾値ランニングのペースで最初から最後まで走ることは難しいようです。そのため、一部の指導者・ランナーが閾値ランニングと呼んでいる練習とは徐々にペースを上げて、後半に閾値ランニングペースに達するという練習を行っており、本当の閾値ランニングペースは一部のようです。
インターバルトレーイング
インターバルトレーニングとは、激しい運動と休憩を断続的に繰り返すトレーニングです。ランニングでは3~5分程度維持出来るペースが目安と言われています。
インターバルトレーニングの目的は、VO2max(最大酸素摂取量)を最大限に高めることと言われいます。
完全に休憩した状態からVO2maxに到達するまでには90~120秒かかると言われており、インターバルトレーニングの開始は3~5分かけるのが適正であるとされています。2回目・3回目と回数を重ねていくにつれて、VO2maxに到達するまでの時間も短くなっていくため、休憩時間を短く保つ場合は3~5分よりも短くしても問題ないとされています。
レぺテンショントレーニング
レぺテンショントレーニングの目的は無酸素性能力・スピード・ランニングエコノミーを高めることと言われています。
※ランニングエコノミー:ランニングの効率性を示す指標で、より少ないエネルギーで走れる状態を指します。
レぺテンショントレーニングの例として、400mを全力+休憩3分×10セットがあります。
レぺテンショントレーニングは強度が高い為、十分に身体を回復させてから正しいフォームで走ることが重要であるとされています。
レぺテンショントレーニングはトレーニング強度を上げていく過程で休憩時間を短くすることはあまり勧められていません。休憩時間が短くなると回復が不十分になり、フォームが崩れてしまう可能性があります。
まとめ
スポーツレベルとしてのランニング・トレーニングは、走った距離ではなく、トレーニングの強度とそれに伴う時間で考えた方が良いとされています。熟練のランナーのランニング距離を参考にしても、設定した距離を走り切るには熟練ランナーよりも時間がかかってしまいます。
今行っているトレーニングの目的と強度を理解し、時間を設定することが大切です。闇雲にやってしまっては十分な効果が得られない可能性があるだけでなく、ケガ・熱意の消失によりトレーニングを中断する可能性も出てしまいます。
熟練の長距離ランナーは1週間など定期的な期間内のトレーニング内容と時間・距離を記録しています。
記録をつけて徐々に負荷を強くしていき、ランナーとして充実なトレーニングに励んで下さい。
参考書籍
ダニエルのランニング・フォーミュラ第4版 著者:ジャック・ダニエルズ
 T療法士のヘルスケアクリニック!!
T療法士のヘルスケアクリニック!!