この記事に興味を持って頂きありがとうございます。理学療法士・アスリートとして得た「皆様の健康に役立つ情報」を日々発信しています。
ダイエットを始めるきっかけは人それぞれですが、ダイエットを成功させる上で食事は運動以上に重要な要素です。
SNSなどでは様々なダイエット方法が発信されていますが、理学療法士・アスリートとして身体にとって危ないなと感じる方法もあります。
結局のところ、健康的・リバウンドせずに痩せるためには、運動の継続に加えて日々の食事管理が欠かせません。
しかし、「何を食べたらいいのか分からない」「手間がかかるから続かない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事ではダイエット中の食事を考えるポイントについて解説していきますので、ダイエット生活の参考にしてみて下さい。
カロリーを計算

体重を落とすには摂取カロリーが消費カロリーを下回る必要があります。つまり、日々のアンダーカロリーを作らなければどれだけ運動を継続していても痩せることは出来ません。
消費カロリー人によってそれぞれですが、消費カロリーの目安は計算することが出来ます。
【例】
30歳女性、身長160cm、体重60㎏、デスクワーク中心で週2~3回の軽めの運動
【1.基礎代謝量】
=10×60+6.25×160ー5×30ー161
=600+1000ー150ー161=1289kcal
【2.活動係数】
=1289×1.55=約1997
【3.ダイエット用】
=1997kcalー500=約1500kcal
➡約1500kcal/日が目安
PFCバランスを整える
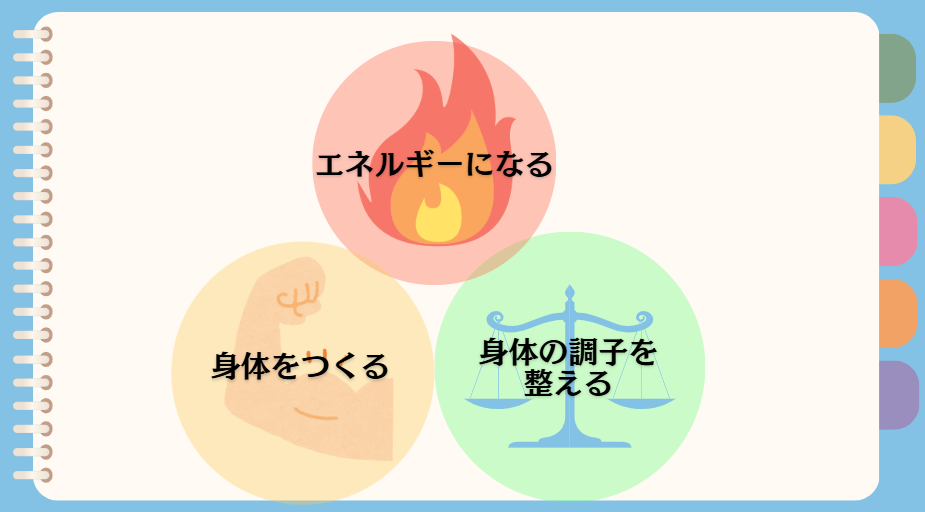
カロリーだけを意識するダイエットは、短期的な体重減少にはつながるかもしれgませんが、健康的ではありません。体の機能を正常に保ち、筋肉量を維持しながら脂肪を減らすためには、タンパク質・脂質・炭水化物バランス(PFCバランス)を考えて摂取することが不可欠です。
P(タンパク質):体重の1.2~1.5g➡筋肉量や代謝の維持、肌・髪などの美容に必要
F(脂質):総カロリーの20~30%➡ホルモンバランスや満足感に必要
C(炭水化物):残りのカロリー➡脳・筋肉を働かせるためのエネルギー源
例:30歳女性、身長160cm、体重60㎏、デスクワーク中心で週2~3回の軽めの運動
約1500kcalの内訳
タンパク質=60(体重)×1.4=84g/日
脂質=1500×0.25=375kcal=375/9=42g/日
炭水化物=1500ー84×4(タンパク質摂取によるカロリー)ー375kcal(脂質摂取によるカロリー)=789kcal=197g
タンパク質:84g
脂質:42g
炭水化物:197g
【意識するポイント】
低脂質+高タンパク質+適量の炭水化物
高タンパク質を意識

炭水化物・脂質は嗜好品に多く含まれているため、多くの方にとって意識せずとも摂取することが出来ます。しかし、タンパク質は意識しなければ一日に必要な摂取量を取ることは難しい場合が多いです。
タンパク質は、人の身体を構成する成分です。食事から摂取したタンパク質がアミノ酸に分解されて、身体に吸収されると筋肉や臓器、肌、髪、爪などの材料になる他、ホルモン・代謝酵素・免疫物質などに変化し様々な働きをしています。
身体のタンパク質は合成と分解が繰り返されているため、合成と分解のつり合いをとるには食事からタンパク質を摂取することが必要です。髪・爪が伸びるように、身体のタンパク質は新しく作られる一方で抜け落ちて失われているものもあります。また、筋肉や臓器といった目に見えないものも一部分解されて、体外へ排出されます。こういった失うものを補うためにタンパク質摂取を心がけることが大切です。
タンパク質の代表的なものとして、肉・魚・乳製品・大豆製品などが挙げられるため意識して摂取することがポイントです。
サラダだけのような食事制限はタンパク質量が足りず、筋肉量が減少しリバウンドしやすい身体になってしまいます。
高タンパク質のために取り入れたいメニュー

高タンパク質食事メニューのメリット
間食・嗜好品のポイント

食べる時間帯:夕食後や就寝前は避けることが望ましく、食後2~3時間後の午前10時や午後3時頃に済ませるのが理想です。
間食の量:間食でもカロリーを摂取するとオーバーカロリーの原因となってしまいます。少量でも満足できるように、ゆっくりとよく噛んで食べることを心がけて下さい。
目的:空腹を満たす・栄養補給など、目的を明確にして食べることが大切です。感情的な食欲で食べるのは避けることが望ましいです。
続けられる工夫をする
ダイエットは継続出来る生活習慣・食習慣でないと失敗してしまいます。「体型は生活習慣に出る」とよく言われますが、ダイエット中の食習慣を維持することが出来ず、いずれ食習慣が元に戻してしまうと体型も元に戻ってしまいます。
そのため、ダイエットを成功させるためにはダイエット中の食習慣が果たして継続出来るものなのかを自身に問いかける必要があります。
もし、今の食習慣が無理をして我慢し続けており、ストレスがたまるのであればプランを考え直さなければいけません。
ダイエットのために好きなものを完全に断ってしまっている場合は、週に1回食べても良いことにし、その分運動をするなど工夫してみてはいかがでしょうか?
ダイエットは一朝一夕で結果が出るものではありませんので、ご自身のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる食事改善を見つけることが大切です。
 T療法士のヘルスケアクリニック!!
T療法士のヘルスケアクリニック!! 

