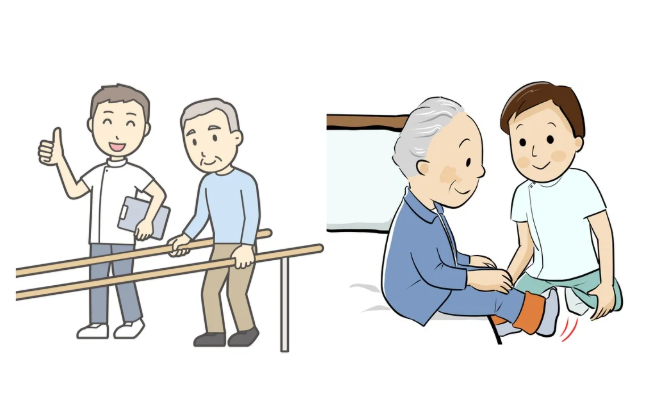理学療法士としての仕事は急性期病院・回復期リハビリ病院・生活期の通所リハビリや訪問リハビリなど様々な環境があります。
今の職場で働いていると「もっと自分にあった環境があるのではないか」と考えたり、キャリアアップなどの転職を考えたりすることもあると思います。
ここではリハビリ病院・介護老人保健施設・通所リハビリ・訪問リハビリを経験した私がそれぞれの職場の働き方や環境をお伝えしていきます。
あくまでも個人的な経験ですが、働く環境を考える材料にして下さい。
回復期:リハビリテーション病院
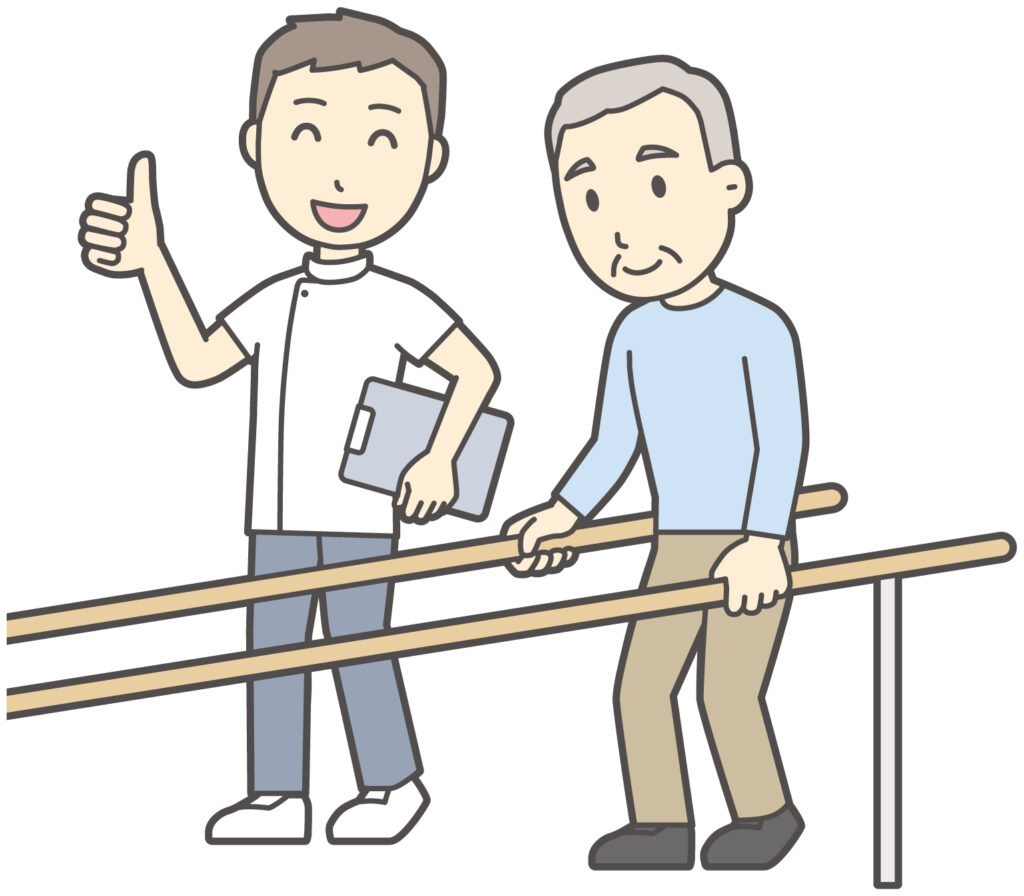
回復期リハビリテーションはリハビリの効果が最も期待出来る段階であると思われます。患者さんは状態が安定した方がリハビリ病院に転院してくるため、急性期病院よりはリスクが低いため若手が働きやすい環境です。
1日のスケジュール
私が経験したリハビリテーション病院では、管理職が調整したスケジュールによって一日のリハビリをする対象者と時間が決まっているため、組まれたスケジュール通りにこなすことで一日が終わります。
リハビリ病院ではリハビリの単位数をこなすことが病院の収入に繋がるため、出来るだけ単位数をこなすことが求められます。リハビリの単位数は法律上、1日24単位(8時間)、1週間で108単位(36時間)までと決まっており、リハビリ病院では一日に18~22単位を目安にリハビリをこなします。
患者さん個々の一日に出来るリハビリ上限時間は決まっており、2025年時点で脳卒中・廃用症候群では1日に最大9単位(3時間)、運動器では最大6単位(2時間)となっています。
多くの場合、脳卒中患者は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の3職種で3単位ずつ(1時間)リハビリを行い、廃用症候群では理学療法士・作業療法士が3単位×2回(2時間)・3単位と分けてリハビリを行います。
運動器では理学療法士・作業療法士で2単位(40分)×3と分けることが多いです。
リハビリ病院では患者さんの生活の再獲得に向けてリハビリに特化した環境であり、集中してリハビリに取り組めるようにリハビリ時間が長いことが特徴です。
患者の特性

リハビリ病院の患者さんは転倒による骨折や脳出血や脳梗塞などの脳卒中、その他の病気により身体が弱ったことなどが対象です。
そのため、リハビリ病院に転院してくる患者さんは望んで入院・リハビリ病院に転院した方ではなく、他の環境と比べて心身共に弱っていたり、ストレスが溜まっている方が比較的多くなります。
病院という閉鎖的な環境でストレスが溜まっている患者さんや認知症などにより入院していることが分からずリハビリを拒否する患者さんがいらっしゃいます。そういった方々も上手く対応しリハビリをこなしていく能力が必要になります。
やる気に満ち溢れた患者さんもいらっしゃいますが、ストレスが溜まっている人やリハビリ拒否をする人などを対応することも多いため、対人のストレスが溜まりやすいため注意が必要です。
担当する患者の人数
リハビリ病院では患者さん一人当たりのリハビリ時間が合計2~3時間と長いため、リハビリの担当数は他の職場環境と比較し少なくなります。リハビリ病院は365日リハビリをするため、一日に担当する患者さんと休んでいるの療法士が担当する患者さんのリハビリを行います。
そのため、一日にリハビリする患者さんの人数・時間から担当する患者さんは3~5人となることが多いです。比較的担当する患者さんの人数が少ないため、患者さんの情報や状態は把握しやすくなります。
働く環境
リハビリ病院はリハビリに特化した環境や設備が整っており、環境や設備不足でリハビリに困ることは比較的少ないです。また、ドクターや看護師が常駐しているため、患者さんの急変時には対応してくれるため比較的安心して働くことが出来ます。
リハビリ病院では看護師と連携をとることが多く、患者さんの状態や能力を共有し、患者さんを徐々に自立させていきます。時には看護師から担当する患者さんの「移動が自立出来ないか」などの相談を受けることもあります。
どのような職場環境でもそうですが、リハビリ病院では特に看護師やドクターと連携することが求められます。
管理する業務
リハビリ病院では患者さんのリハビリを行うために「総合実施計画書」という書類を作成します。これはどういった計画でリハビリを進めていくのかを記載する書類であり、他の職種と合わせて毎月作成する必要があります。
また、患者さんの状態を多職種と共有するために定期カンファレンスが毎月行われます。定期カンファレンスの前に話す内容を事前に記入しておくなどの準備が必要です。
担当する患者さんが少ないため管理する書類業務は少なく、比較的自身の書類業務は管理しやすい印象です。
介護老人保健施設

介護老人保健施設を簡潔にいうと、回復期リハビリ病院と在宅の中間のイメージです。リハビリ病院ほどリハビリに特化した施設ではなく、あくまでも生活を中心とした環境です。
介護老人保健施設ではリハビリにより心身の自立を促すというよりは、生活の中で心身の自立を促していく環境です。そのため、介護老人保健施設の中心は療法士ではなく介護士となります。
1日のスケジュール
私が経験した介護老人保健施設では一日にリハビリを行う利用者のみ決まっており、リハビリする時間はリハビリ病院とは異なり決まっていませんでした。1日に18~20人程の利用者のリハビリを行うことが多く、施設を回って利用者に声掛けしリハビリを順次行っていく環境です。
リハビリを行う時間は決まっていないため、どの時間帯に、どの利用者のリハビリを行ったり、仕事をどのよう進めていくかは自由です。
しかし、スケジュールが決まっておらず時間の過ごし方は自由ですが、一日の就業時間以内にリハビリを行う利用者全員を回らないといけないため、タイムプレッシャーがありました。
午前中に9人済ませておきたかったけど8人しか出来なかった時は、午後に少しタイムプレッシャーを感じました。また、利用者ごとにリハビリを行って欲しい時間帯の希望がある場合があり、利用者を回る順番を工夫する必要がありました。
時間管理に自信がある方は向いているかもしれませんが、私のようにタイムプレッシャーを感じる方は少しストレスを感じるかもしれません。
利用者の特性
回復期リハビリ病院と比較し自由に過ごしている利用者も多い為、ストレスによりイライラしている人やリハビリ拒否をする方は比較的少なくなる印象です。しかし、リハビリ拒否をする人が全くいないわけではありませんでした。
利用者の場所まで行きリハビリの声掛けをしたのに、リハビリ拒否されたので別の人で一旦リハビリを行い、後々時間が経過してから再度リハビリの声掛けをするということも珍しくありません。
利用者ごとの特徴を理解し、比較的リハビリを行ってもらいやすい時間帯や誘導しやすい声掛けといった工夫を個別で行っていくことが求められる印象です。
担当する利用者の人数
私が経験した介護老人保健施設では療法士1人当たりの担当する利用者は約16~20人程度が多かったです。16~20人を担当するため、リハビリ病院と比較し利用者の特徴や経過、今後の流れを全員把握しておくのは少々大変かもしれません。
経験を積んでいけば慣れていきますが、最初は担当する人数に戸惑うかもしれません。
働く環境
リハビリ病院は看護師と連携をとることが多かったですが、介護老人保健施設は介護士が中心であり、介護士と連携をとっていくことが多いです。介護老人保健施設から自宅に向けて退所させるために、施設内の生活の中で自立を促して欲しい所や転倒リスクの高い所、誘導して欲しいところなどを積極的に共有していきます。
また、介護老人保健施設はリハビリ病院と比較し患者・利用者の人数に対してスタッフの人数が少なくなります。利用者50人に対して、介護士が5人など少ない人数で対応していくことが求められ、利用者の独力を止めたりするなど療法士も手伝う場面は多々あります。
時折、ケアマネージャーと話し合いを行ったり、外部の福祉業者と連携をとったりなどの外部とのコミュニケーション能力が求められ、最低限の社会人マナーは求められます。
また、入所されてきた利用者の家を調査するために訪問することは多々ある為、車の運転に慣れておくとよいかもしれません。
管理する業務

介護保険分野はリハビリ病院と比較し書類業務が多くなる印象です。担当する利用者も多く、行う書類業務も非常に多いため書類の期日の管理を行うことが大変です。
頭の中だけで書類業務を完璧にスケジュールや進捗を管理することは難しいため、きちんと管理出来るように工夫する必要があります。
工夫方法としてスケジュール手帳を利用すると書類業務の締め切りや進捗は管理しやすくなる印象です。
通所リハビリ

通所リハビリは自宅で過ごしている方が、現状の身体機能や生活能力を維持・向上させる目的で利用している方が多いです。自宅で過ごしているため比較的ストレスが少なく、リハビリ病院・施設と比較し明るく過ごしている方が多くなる印象です。
1日のスケジュール
通所リハビリは基本的の担当している利用者が、通所リハビリにおられる時間帯の内にリハビリを行います。通所リハビリを提供している施設によって異なりますが、利用者全員が90分間通所リハビリを利用し帰宅、その次に全員が90分間通所リハビリを利用するなど午前2回・午後2回のサイクルでこなすところや、利用者ごとに利用開始する時間帯や利用時間が異なる施設もあります。
利用者が通所リハビリを利用する時間帯の内にリハビリを提供しないといけないため、人手が足りない時はリハビリをこなす人数が多くなり、少しタイムプレッシャーを感じるかもしれません。
利用者の特性
リハビリ病院・施設と比較し状態が安定している方が多くなります。通所リハビリの特性により異なりますが、リハビリ特化型の施設では自立している方が多く、リハビリに意欲的な方が多くなる印象です。施設によっては要介護で介護が必要な人を中心にリハビリを行う場合もあるかもしれません。
担当する利用者の人数
通所リハビリは施設により異なると思いますが担当する利用者は最も多くなると思われます。一日あたり10~16人程度の担当利用者×5(月~金曜日)=50~80人となります。週2回以上来ている利用者もいるため、80人担当するということはないと思われますが、それでも担当する利用者は必然と多くなります。
利用者は自宅で過ごしているため、リハビリ病院・介護老人保健施設と比較し、細かく利用者の状態を把握する必要はないかもしれませんが担当する人数が多いため人によっては少々大変かもしれません。
働く環境
通所リハビリの施設によりますが、利用者はリハビリをしに来ているため最低限以上のリハビリ設備は整っていると思われます。施設によりますが、看護師と連携をとったり、療法士間で連携をとるなどします。
個々で利用者を担当するため、リハビリ病院・介護老人保健施設ほどは同一施設内での利用者の情報を共有するなどの連携は求められない印象です。しかし、その分ケアマネージャーと情報を共有することは多くなり、利用者の変化などがあればケアマネージャーに電話するなど外部の人とコミュニケーションをとる能力が求められ、最低限の社会人マナーを身に付けておく必要があります。
また、サービス担当者会議といいケアマネージャーを中心とした会議を利用者の自宅で行うこともあるため、車の運転が求められる時もあります。
管理する業務
担当する利用者が多いため、管理する書類は必然と多くなります。施設によっては利用者との契約を療法士自身で行わないといけないところもあるため、利用者に関する書類業務を管理するのは少々大変かもしれません。
訪問リハビリ

訪問リハビリは車や自転車などを用いて利用者の自宅まで行き、リハビリを行う環境です。
1日のスケジュール
訪問リハビリは制度上3ヶ月ごとの契約の更新制です。利用者ごとに訪問する曜日と時間が決まっており、特に予定の変化がなければ予定通り一日訪問しリハビリをこなしていきます。
訪問リハビリは利用者の家に行ってリハビリを行ってくるということから、療法士・曜日ごとに出発する時間帯や休憩時間・帰宅時間が異なります。利用者の住所やリハビリ時間によって、早く戻ってこれたり、時間ギリギリに戻ってくるということもあります。
また、訪問する利用者の住所・リハビリ開始時間によっては少し休憩することも出来るため、道中コンビニにトイレ休憩に行ったり、車の中で休憩が出来る時もあります。
患者の特性
訪問リハビリは自宅でリハビリを行うため、重症者で気軽に外出が出来ない方や外歩きを行う方など身体能力・動作能力はバラツキがあります。
利用者の能力・希望に応じて、限られた環境下でリハビリを提供する能力が求められます。
担当する患者の人数
一日に訪問する件数は4~6件であることが多く、平均して1週間で25件訪問します。1週間で2回訪問する利用者もいらっしゃいますので、勤務先によりますが担当者は20~25人となることが多いと思われます。
働く環境
自転車や車で自宅まで訪問しリハビリを提供する特徴から、夏場は暑さ・冬は寒さに耐える必要があります。病院・施設のような内部が整った環境下で仕事をするわけでなく、移動し自宅でリハビリを行うため環境の変化を大きく受けます。
特に夏場の車は社内温度が高く、熱中症に気を付けなければいけません。
また、車などの道中の移動では事故などに気を付けなければいけません。車の運転に慣れている方であれば共感いただけるかもしれませんが、危ない運転をしている方は意外と多いものであり、事故には十分に気を付けなければいけません。
訪問する利用者の中には、掃除が行き届いておらずゴミが散乱していたり、散らかっている家もあるため、潔癖症な人は難しいかもしれません。
訪問リハビリは特にケアマネージャーと連携をとることが多く、利用者の転倒や体調変化、福祉用具の変更、訪問リハビリの日時に変更などがあった際は連絡をとらなければいけないことが多いです。外部との連携が多いため、非常に社会人力とマナーが求められることになります。
管理する業務
訪問リハビリは管理するものが非常に多いです。利用者全員の計画書・ケアマネージャーへの報告書などの書類業務や利用者からの休みや日時変更があった際のスケジュール管理、車をコインパーキングに止めるためのお金の管理、ガソリンの管理などなど自身で管理・調整しなければいけないものが多々あります。
基本的に自分自身で全て管理しなければいけないため、自己管理能力が非常に求められます。自己管理に自信が無い人は訪問リハビリは難しいかもしれません。
 T療法士のヘルスケアクリニック!!
T療法士のヘルスケアクリニック!!